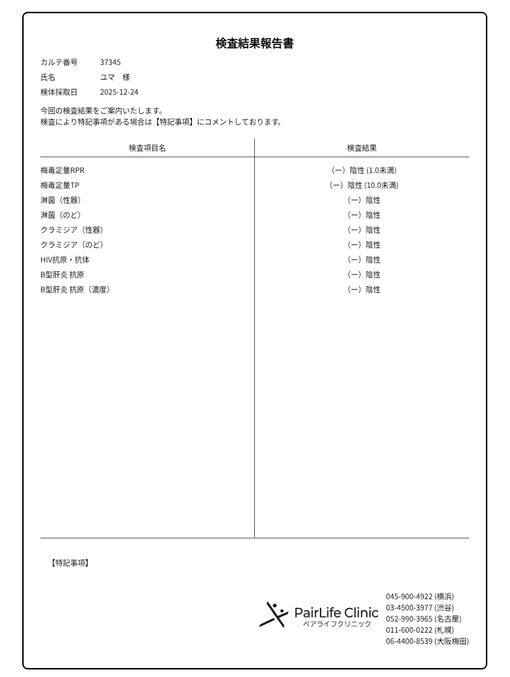暗闇の中、目隠しをされたまま、あなたは静かに息を整える。空気が肌を撫でるように冷たく、次に何が起こるのか分からない緊張が、胸の奥で甘い疼きを生んでいる。
突然、耳元で囁く声。
「ちょっと、熱いかも……でも、すぐに癖になるよ」
次の瞬間、太い蝋燭の先から熱い雫が落ちた。背筋が一瞬、ピクリと跳ねる。熱い——けれど、その痛みは想像していたよりも遥かに甘美だった。温もりが肌の上で広がり、冷めるにつれてじわじわと心地よい感覚に変わっていく。
もう一滴。肩口に落ちると、今度は思わず声が漏れそうになった。ゆっくりと滑り落ちる蝋の軌跡が、まるで肌を這う指のように官能的で、熱さと冷たさの交錯が、さらに欲望を刺激する。
「ほら、もっと感じてみ?」
囁きとともに、さらに深く、さらなる熱が与えられる。じんわりと焼き付けられる感覚は、痛みと快楽の境界線を曖昧にし、あなたの身体はその狭間で翻弄される。
熱に溶かされていく自分を感じながら、もっと……もっと欲しくなる。

 03-3528-6814
03-3528-6814